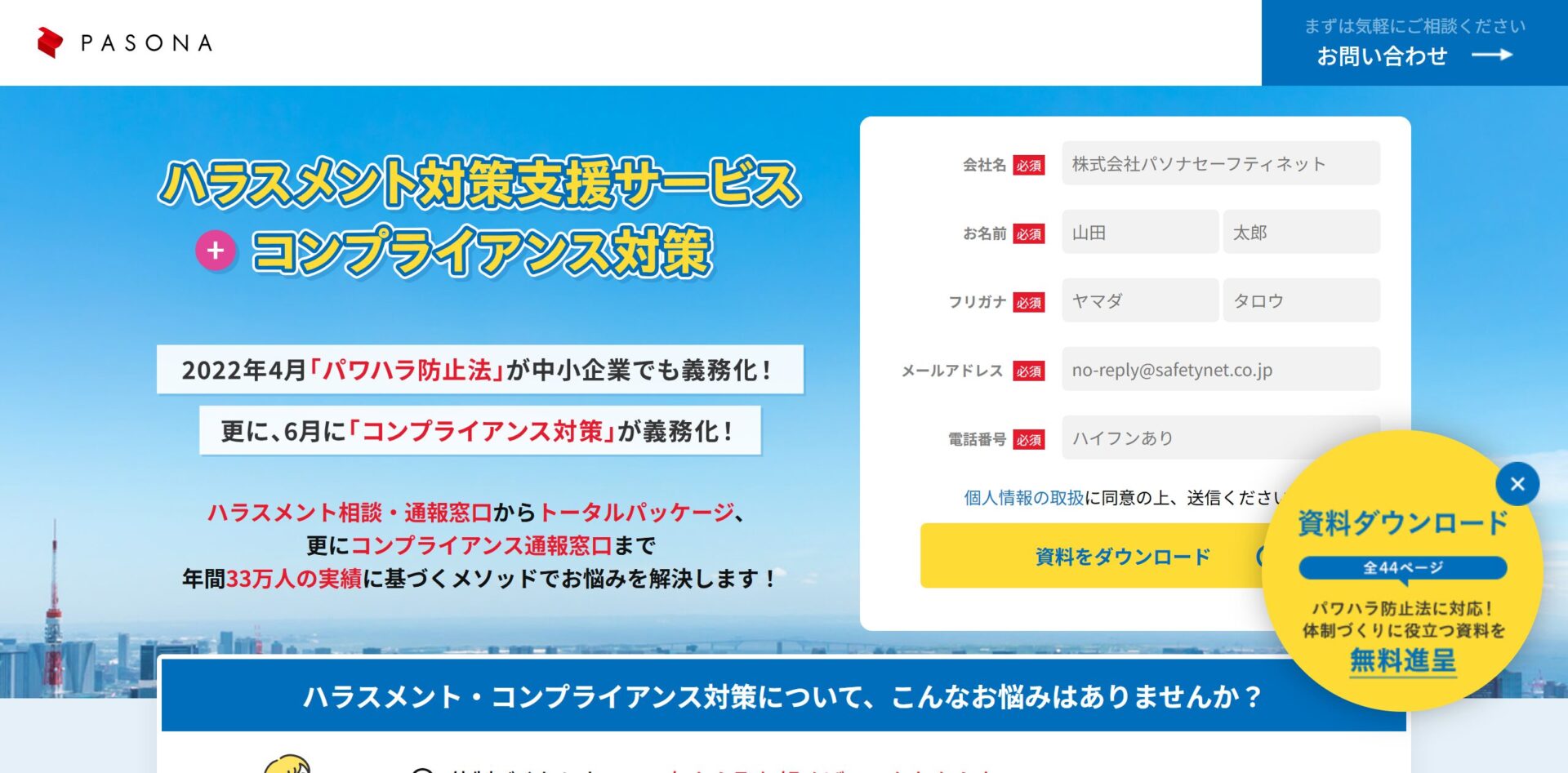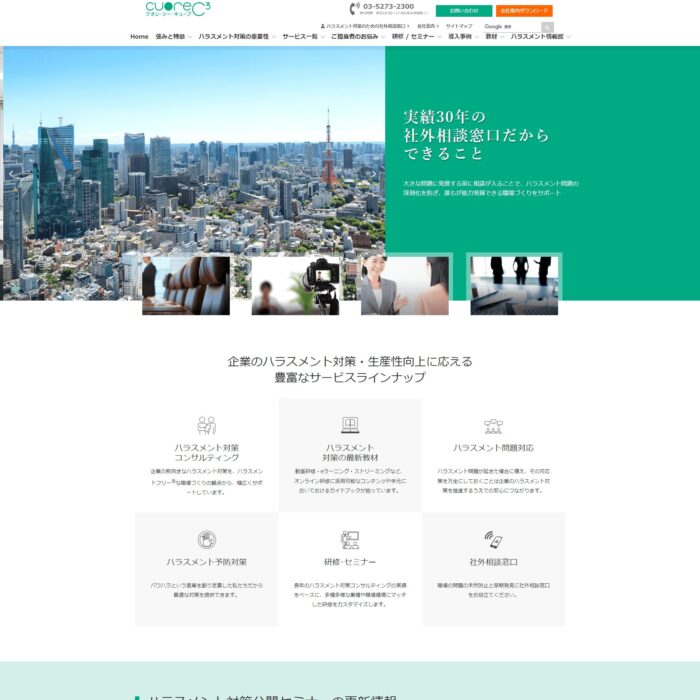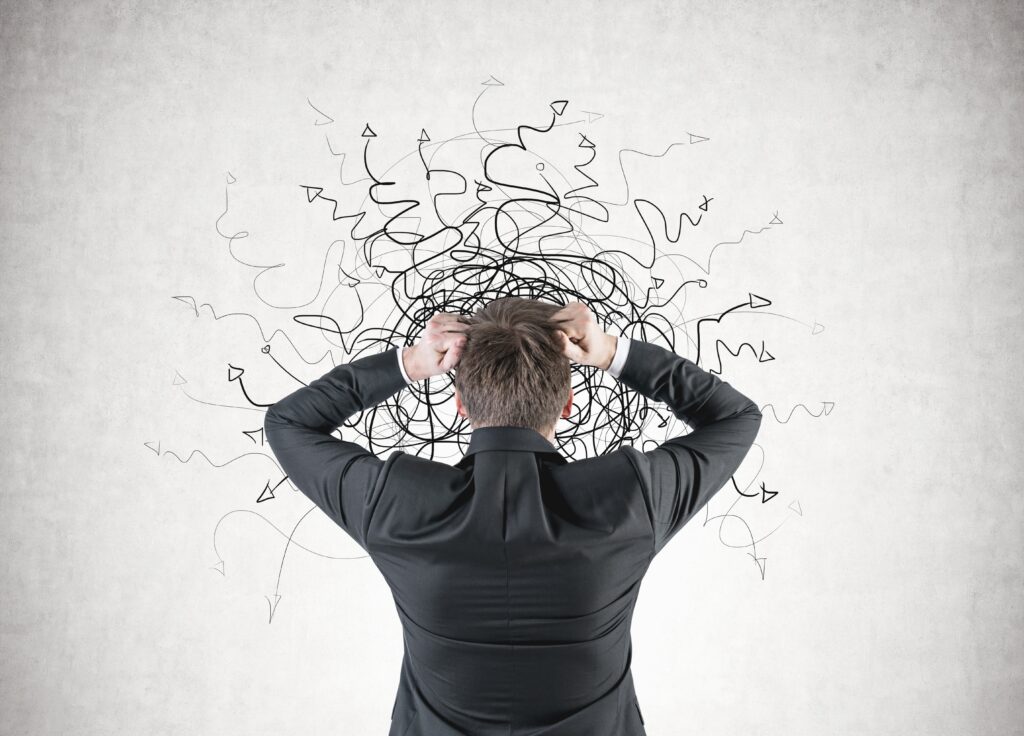職場でのハラスメントやメンタルヘルスの問題に早期対応するためには、相談窓口の設置が欠かせません。安心して相談できる環境をつくることで、従業員の働きやすさや職場の健全性にもつながります。環境づくりには、何点か押さえるべきポイントがあります。本記事では、相談窓口の設置手順と信頼される運用のコツを紹介します。
相談窓口の設置手順と基本方針の決め方
相談窓口を設けるには、目的を明確にしてから体制を整えることが重要です。まずは、どのような相談に対応するのかを決め、必要な範囲に応じて体制や対応部署を定めます。
対応する内容を明確にする
相談窓口の目的が曖昧だと、運用がぶれてしまいます。パワハラやセクハラなどのハラスメントを中心に扱うのか、労働条件やメンタルヘルスの相談も含めるのか、会社としての方針をはっきりさせましょう。対象を広くしすぎると対応が難しくなるため、最初は明確な領域に限定することも選択肢のひとつです。
社内合意と担当体制の構築
方針が決まったら、人事部門や衛生委員会などと連携し、具体的な運用体制を組みます。誰が相談を受けるのか、記録の扱いはどうするのかといったルールを整理し、必要であれば弁護士や社労士の協力も視野に入れましょう。信頼性のある体制にすることで、従業員も安心して相談しやすくなります。
従業員への告知と導入初期の準備
相談窓口をつくっても、存在が知られていなければ意味がありません。社内ポータル、メール、社内掲示板などを通じて、相談内容の例や受付手段、窓口担当者の情報をわかりやすく周知しましょう。告知の際には「相談しても不利益はない」と明示することで、心理的なハードルも下がります。
相談しやすさを高める工夫と運用のポイント
相談窓口が設置されていても、実際には利用されないことも少なくありません。安心して声を上げてもらうには、制度面と運用面の両方から配慮が必要です。
相談手段を複数用意する
一人ひとりの状況に合わせて相談できるよう、対面以外の方法も準備しましょう。電話やメール、社内チャット、匿名フォームなど複数の相談ルートを確保しておくと、利用の幅が広がります。とくに匿名での相談受付があると、初めての相談でも心理的な負担が軽くなります。
秘密保持と信頼構築のルール
相談者の情報が漏れたり、評価に悪影響が出たりするといった不安をなくすためには、秘密保持の姿勢を明確にすることが重要です。相談内容は社内で共有せず、必要最小限の関係者にのみ伝えるなど、管理体制を徹底しましょう。また、相談者の話に真摯に耳を傾け、事実確認や記録の扱いについても丁寧に対応することで、信頼関係が築かれます。
担当者の育成と相談対応力の向上
窓口担当者の対応が不十分だと、相談者が失望して二度と利用しなくなることもあります。相談の基本姿勢や対応マニュアルを用意し、担当者には定期的に研修を実施しましょう。自分で対応できない内容が来たときには、専門家へスムーズにつなげられるよう、社外の連携先もあらかじめ用意しておくと安心です。
社内外の連携でさらに利用しやすい環境を整える
相談窓口の機能を強化するには、社内体制の強化と同時に外部リソースの活用も検討しましょう。従業員にとって「相談してよかった」と思える仕組みづくりが大切です。
周知の継続と相談しやすい雰囲気づくり
窓口を設置したあとも、定期的に存在を知らせる取り組みが求められます。社内報、研修資料、会議の冒頭などを活用して「困ったらここに相談できる」という意識を社内に浸透させましょう。管理職にも「受け止める姿勢」の重要性を伝え、相談に対してネガティブな反応を示さないよう意識づけることが必要です。
外部相談窓口の導入を検討する
社内に相談しにくいと感じる従業員のために、外部の第三者機関を相談先として用意する方法もあります。専門の相談会社や社労士事務所に委託することで、客観的な立場からの対応が可能になり、従業員も安心して相談できます。社外との連携は、社内では見えにくい課題の発見にもつながります。
相談後の対応フローを整える
相談を受けたあとにどのように対応するかは、企業の信頼を左右します。ヒアリング内容の記録方法、関係者との連携、事実確認の手順、再発防止策の検討など、対応の流れを事前に明文化しておくと、トラブル時にも冷静に対応できます。対応の経過は可能な限り相談者にも共有し、不安を感じさせないように配慮することが大切です。
まとめ
社内相談窓口は、単に設置するだけでは意味がなく、従業員が安心して利用できる仕組みと運用が整っていることが重要です。まずは目的や相談対象を明確にし、社内の合意を得ながら適切な体制をつくりましょう。相談手段を複数用意し、秘密保持や信頼関係の構築を重視した対応を行うことが、相談しやすさにつながります。さらに、定期的な周知や担当者の研修、外部窓口の活用によって、制度としての信頼性を高めることができます。職場に安心して声を上げられる窓口があることで、従業員は働きやすさを感じやすくなり、結果として離職防止や職場環境の改善にもつながります。相談を「特別なこと」ではなく「身近な手段」として定着させることが、これからの企業には求められています。
-
 引用元:https://www.safetynet.co.jp/
心の専門家集団による"自社専用のハラスメント対策"
引用元:https://www.safetynet.co.jp/
心の専門家集団による"自社専用のハラスメント対策"- Point
導入実績:法人企業2,000社+中央省庁、自治体他 / 年間33万人
- Point
会員数:150万人
- Point
専門家在籍:公認心理師、産業カウンセラー、臨床心理士、看護師、栄養士、ファイナンシャルプランナー、警察OB など
- Point