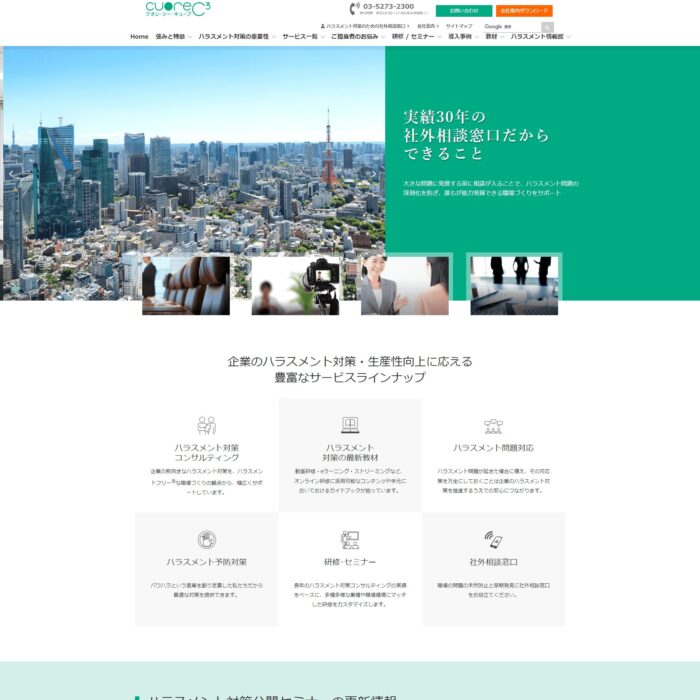近年、職場で起こるハラスメント相談件数は、年々増加しています。ハラスメント対策は事業主の義務であり、ハラスメントを放置すれば、法的責任を問われる可能性があり注意が必要です。自社でハラスメントが起こった場合、損害は計り知れません。会社が大きいほど、無視できないリスクとなります。また、ハラスメントが起きた会社は、社会的信用やイメージが大きく損なわれます。さらに、ハラスメントが原因で、優秀な人材がやめてしまうリスクにもつながりかねません。 ハラスメントが起こるリスクを減らすためには、相談窓口の設置や研修の実施など、積極的なハラスメント予防対策が必要です。
データで見るハラスメントの実態
厚生労働省のデータによると、総合労働相談コーナーに寄せられるハラスメント関連の相談件数は年々増加傾向にあります。2020年度までの過去3年間には、パワハラ、セクハラの相談件数が多くあり、2022年にはパワハラにおける調停件数が1400件を超えています。
また、ハラスメントの被害者は、男女ともにどの世代にも見られますが、特に女性や派遣社員に多い傾向です。一方、加害者は、上司や同僚が多く、強い立場の者が弱い立場のものにハラスメントする傾向が強いのが現状です。
企業がハラスメントによって受ける損害は、決して少なくはありません。まずハラスメントが起これば、賠償金の支払いが必要になります。さらに、職場での生産性の低下や、従業員のモチベーション低下が起こるリスクもあるでしょう。また、ハラスメントが原因で優秀な人材が退職することで、企業にとって大きな損失となります。
効果的なハラスメント防止対策の実践
企業がハラスメントを防止するためには、組織体制の整備や相談や通報がしやすい体制の整備、就業規則や行動指針の整備が必要です。ハラスメントによる被害者を出さないためにも、今からできる対策を徹底して行う必要があります。
ハラスメント研修や組織の整備などを事前に行っておくことで、ハラスメントを許容しないという経営陣の姿勢を見せることができます。さらに、正しいハラスメントの知識を全社員に共有することで「ハラスメントではなくコミニュケーションだと思っていた」というすれ違いも回避できるでしょう。
組織体制の整備
企業のハラスメント対策では、組織体制の整備が重要です。まず、ハラスメント防止委員会を設置し、経営陣、管理職、従業員代表など、様々な立場から構成員を選出します。様々な立場から構成員を選出することで、より広い視点からハラスメント問題に取り組むことができるでしょう。
また、ハラスメント相談窓口の担当者や、ハラスメントが発生したときに対応する責任者を決めておく必要もあります。それぞれの役割を決めておくことで、ハラスメントの被害者が安心して声を上げられる環境を整えられるでしょう。
さらに、ハラスメントの定義、禁止する具体的な行為、懲戒処分などを具体的に定め、全従業員に周知することで、ハラスメント防止に繋がります。組織体制を整備し、しっかりとハラスメントを抑制できる体制で会社運用していきましょう。
相談・通報体制の構築
ハラスメント対策には、相談や通報しやすい体制を整えることも大切です。まずは、相談窓口を設置し、気軽に相談できる環境を整えましょう。あわせて、社外の専門家に相談窓口を委託する方法もおすすめです。第三者が相談窓口になることで、中立性が保たれ、より安心して相談できる体制を作ることができるでしょう。
また、匿名でハラスメントを通報できるシステムもおすすめです。匿名であれば、周りの目を恐れることなく、事実を伝えやすくなります。 一番重要なのは、相談者や通報者のプライバシーを守り、相談や通報によってデメリットがないことを約束することです。
就業規則・行動指針の整備
ハラスメント防止のためには、就業規則や行動指針をはっきりと提示し、従業員一人ひとりが正しい知識を持たなければいけません。就業規則に、ハラスメントにあたる具体的な行為を記載することで、許されない言動を従業員が確認できます。
また、ハラスメントを行った者に対する処罰についても、はっきり規定しましょう。「ハラスメントは決して許されない」という企業や経営陣の姿勢を示すことが大切です。規則や指針は、研修などを通じて全ての従業員に周知し、定期的な見直しと改善を行いましょう。徹底的に周知し、定期的に見直しを行うことで、ハラスメントを重くみている企業の姿勢が従業員に伝わりやすくなります。
予防・早期発見システム
ハラスメントを未然に防ぐためには、ハラスメントが行われていないかのチェックを日常的に行う必要があります。まず、定期的なアンケートなどの職場環境調査を行い、従業員の声を聞きましょう。アンケートにより、問題になりそうな行動を未然に確認できます。
また、日頃から部下の様子を観察することも大切です。些細な変化に気づき、声をかけることで、問題が深刻になる前に対応できる場合があります。アンケートや管理職の日頃のサポートにより、風通しの良い職場環境が築けます。相談しやすい環境を整えることで、ハラスメントを未然に防げる環境を作ることができるでしょう。
なぜ研修が不可欠なのか
ハラスメント防止には、全従業員への研修を行い、意識を変えていくことが不可欠です。管理職向けには、ハラスメントの定義や法的責任、適切な指導方法などを具体的に伝えましょう。本人の無意識の偏見が、知らぬうちにハラスメントになっている可能性も否定できません。
一般の従業員には、ハラスメントの種類や被害・加害者になった場合の対処法などを教え、ハラスメントの認識を高めます。ハラスメントを見たら報告すること、報告や相談によって不利益が出ないことも周知させる必要があります。
研修は一度きりでなく、定期的に行いましょう。実際に起こりうる事例をもとに学ぶこともおすすめです。パワハラ対策のための研修を行うことで、従業員全員がパワハラの基準、パワハラが起こった時の対処法を学ぶことができます。
実績豊富な研修企業3選
最後に、ハラスメント対策として研修を行いたい企業におすすめの研修企業を3社紹介します。それぞれの会社の特徴が異なりますので、自社に合ったサービスを選んでみてください。
パソナセーフティネット
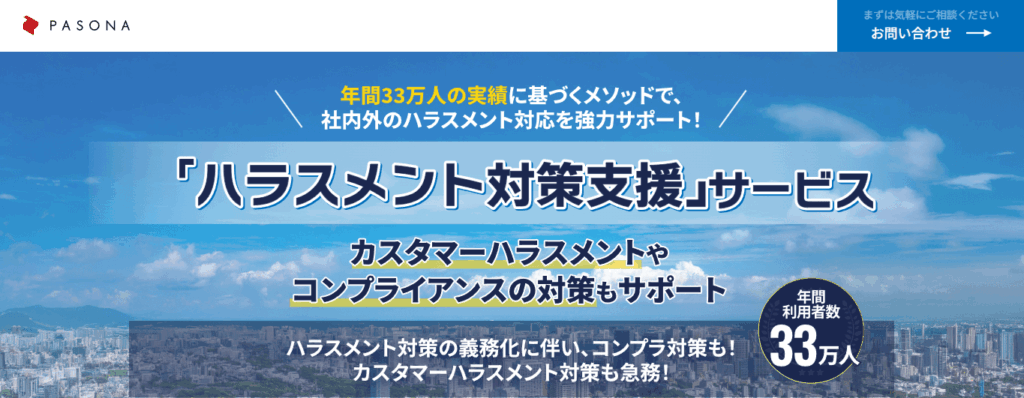
| 会社名 | パソナセーフティネット |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区新橋6丁目16-12 京阪神 御成門ビル7F |
2001年に創業された株式会社パソナセーフティネットは、公認心理師、産業カウンセラー、臨床心理士などの専門家のサポートが受けられることが特徴の会社です。創業から年間33万人の実績があり、厚生労働省が推奨する枠組みを元にハラスメント対策のサポートを行っています。
ハラスメント研修は、1時間7.5万円から依頼でき、要望によってカスタマイズすることが可能です。無料のWebアンケートの実施も可能で、より研修を有意義にしたい会社におすすめです。さらに、従業員が好きな時間にみられる研修動画の提供もあり、研修動画は50名(3ヶ月)10万円から利用できます。
さらに、相談窓口や研修、コンプライアンス通報窓口などを組み合わせた「ハラスメント対策トータルパッケージ」があり、年間17万円から利用可能です。より多方面からハラスメント対策を行いたい企業は、トータルパッケージの利用を検討してみましょう。
導入企業からは、専門家が対応してくれる安心感があると好評で、研修内容をカスタマイズできる点や、豊富な事例に基づいた内容が評価されています。また、相談窓口を任せられる点も好評です。
クオレ・シー・キューブ

| 会社名 | 株式会社クオレ・シー・キューブ |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-5-1 興和一橋ビル別館 5階 |
| 電話番号 | 03-5273-2300 |
株式会社クオレ・シー・キューブは、1990年に設立された会社です。「パワーハラスメント」という言葉を考案した会社で、ハラスメント対策に関する調査・研究を長年行っている特徴があります。
ハラスメント対策研修だけではなく、相談窓口やヒアリング調査、コンサルティングまでを組み合わせたサービスの提供が可能です。ハラスメント対策として、幅広いサポートを行ってほしい企業は、株式会社クオレ・シー・キューブの利用を検討してみましょう。
株式会社クオレ・シー・キューブのハラスメント研修は、基礎的なものから、法律のポイントを解説する研修、ハラスメントが起きたときの実践的な研修など、幅広く用意されています。オンライン・オフラインどちらでも受講可能です。
企業それぞれに合った研修内容を選ぶことができ、オンラインとオフラインで都合の良い方を選ぶことができます。研修後の相談対応やコンサルテーションを通じて、継続的なアフターフォローも可能です。
アドバンテッジ リスク マネジメント

| 会社名 | 株式会社 アドバンテッジ リスク マネジメント |
|---|---|
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2-1-1中目黒GTタワー17階 |
| 電話番号 | 03-5794-3800 |
アドバンテッジ リスク マネジメントは、ハラスメント対策研修をはじめ、従業員エンゲージメント向上、メンタルタフネス度向上研修など、多方面からアプローチできるサービスを提供しています。アドバンテッジ リスク マネジメントの強みは、メンタルヘルスケア事業の知見と、科学的根拠に基づいた独自のプログラムです。
ハラスメント研修は、企業に合わせてカスタマイズが可能で、パワハラ行動改善研修、無自覚ハラスメント防止研修などから選択できます。様々な企業に適した研修により、長期的な改善サポートが可能です。
座学だけではない実践的な研修で、費用対効果は高いと言えるでしょう。また、オンラインとオフラインを組み合わせるなど、継続的な効果を得られやすい仕組みも魅力の一つです。
さらに、ハラスメント対策だけはなく、メンタルヘルス対策やエンゲージメント向上研修などが提供されており、研修後もコンサルティング、各種アンケート調査などで、企業のサポートを行ってもらうことが可能です。継続的なサポートにより、研修の効果を持続させ、ハラスメントのない組織へと導きます。
まとめ
ハラスメント対策研修は、一度実施すれば終わりというものではありません。継続的な取り組みを行うことで、管理職を含めた従業員にことの重大さを理解してもらいやすくなります。経営陣は、本気でハラスメント対策に取り組むという強い意思を示し、組織全体を統率していくことが不可欠です。また、単に規則を作るだけでなく、すべての従業員が「ハラスメントは許されない」という共通認識を持ち、互いを尊重する職場文化を作ることが最も大切です。 ハラスメントのない健全な職場環境を築くためには、企業の社会的責任であると同時に、持続的な成長を実現するための重要な経営戦略と言えるでしょう。