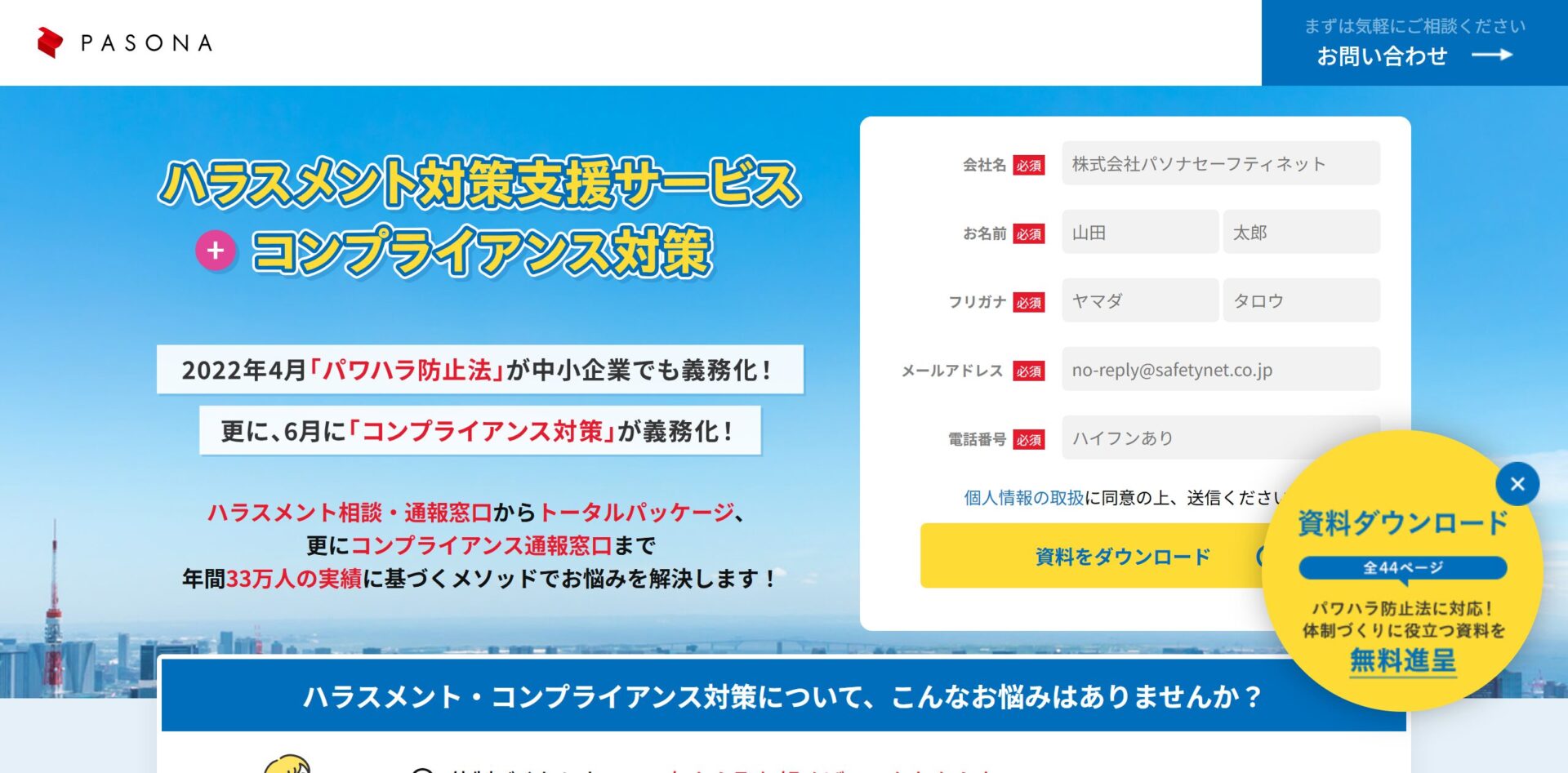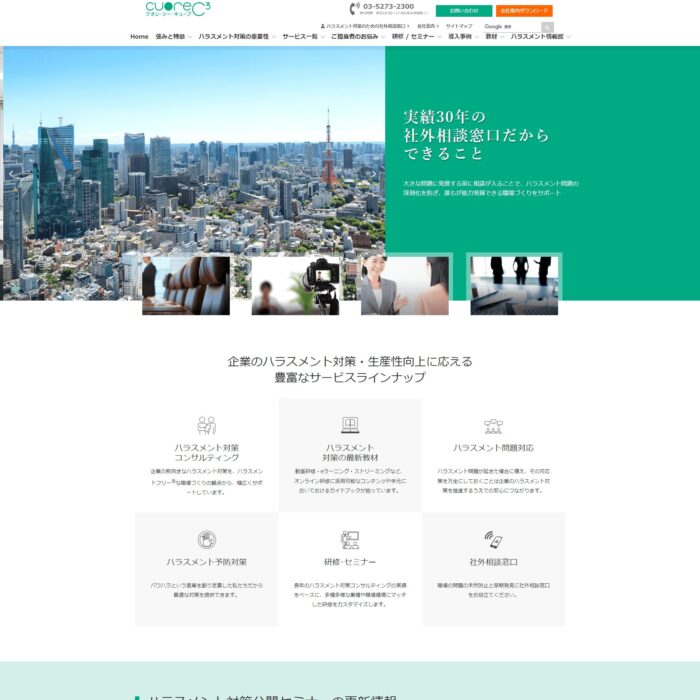顧客からの苦情が行き過ぎて、従業員に精神的な負担を与える苦情ハラスメントは社会的な課題になっています。従業員を守りながら企業の信頼を保つには、苦情ハラスメントに対しての初期対応をどう行うかが大切です。本記事では、企業が理解すべき基本や現場での対応、体制づくりのポイントを紹介します。
苦情ハラスメントを正しく理解する
苦情ハラスメントは、通常のクレーム対応を超えた顧客の過剰な要求や威圧的な言動を指します。内容が商品やサービスの不具合改善を求める範囲を超え、人格否定や脅迫的発言にまでおよぶケースもあります。企業は「正当な苦情」と「ハラスメント的な要求」の違いを理解しておく必要があります。
従業員への影響と企業リスク
苦情ハラスメントを放置すれば、従業員のメンタル不調や離職につながります。職場に相談できずひとりで抱え込むと、うつ病やモチベーション低下といった深刻な問題を引き起こすことがあります。さらに、対応が不適切だと顧客との関係が悪化し、企業イメージの失墜にもつながる恐れがあります。
典型的な事例を把握する
長時間にわたり同じ内容を繰り返す、過度な謝罪や金銭補償を要求する、大声で威嚇し従業員を委縮させるなどが典型例です。とくに近年はSNSでの誹謗中傷を伴うケースもあり、対応を誤ると炎上リスクが高まります。こうした事例を事前に学び、従業員へ周知することが大切です。
定義を社内で共有する
現場の従業員がどこまで対応すべきかを判断できるようにするには、企業として苦情ハラスメントの定義を明確にしておく必要があります。ガイドラインを作成し、社内で共有しておけば、相談や報告がスムーズに行われやすくなります。
現場での初期対応をどう行うか
従業員が苦情ハラスメントを受けたとき、初期対応を誤ると被害が大きくなります。最前線に立つ担当者が守られるよう、企業は現場での行動基準を整えることが欠かせません。
ひとりで対応させない
従業員が過剰な要求を受けた場合、速やかに上司や同僚へ報告し、複数名で対応する体制を整えることが重要です。相手の言動がエスカレートしている状況でひとりに任せると、心理的な負担が強まり、判断ミスにもつながります。
事実を記録に残す
やり取りを正確に残すことは、後の対応方針を決めるうえで役立ちます。日時、場所、発言内容、対応者を詳細に記録し、可能であれば通話録音やメール保存も行いましょう。証拠があれば社内での検討や外部専門家への相談もスムーズになります。
謝罪や回答の範囲を明確にする
正当な指摘には誠実に対応する必要がありますが、事実を超えた過剰な謝罪や金銭的補償は慎重に判断しなければなりません。マニュアルに「謝罪できる範囲」「譲れない一線」を明示しておくと、従業員も安心して対応できます。
危険を感じた場合の対応
暴力的な言動や脅迫が含まれる場合には、安全を最優先にして対応を打ち切り、必要に応じて警察や専門機関に相談することが大切です。従業員に「逃げてもよい」という意識をもたせることで、安心して業務に取り組めるようになります。
相談体制と再発防止の仕組みづくり
苦情ハラスメントを防ぐには、企業全体で相談体制と教育制度を整える必要があります。従業員が声を上げやすい環境と、再発を防ぐ仕組みをセットで考えることが重要です。
社内相談窓口を整える
人事部門などに相談窓口を設置し、従業員が気軽に相談できる仕組みを用意しましょう。匿名相談や外部専門機関との連携を取り入れると、利用しやすさが向上します。相談を受けたあとの対応フローも明文化しておくと混乱を防げます。
教育と研修で意識を高める
現場の従業員には、苦情対応とハラスメントの境界を理解させる研修が必要です。どこから上司に報告するか、どのような発言がハラスメントに該当するかを明確に伝えることで、行動の基準が統一されます。管理職には相談を受け止める姿勢と判断力を養う教育が欠かせません。
外部専門家の活用
悪質なケースや対応が難しい場合には、弁護士や社労士といった専門家との連携が有効です。外部の視点を取り入れることで、企業だけでは見落としやすい課題を補い、より的確な解決策を導くことができます。
再発防止策の徹底
相談事例を集めて分析し、社内のマニュアルや教育内容をアップデートすることが重要です。従業員が安心して働ける環境を維持するためには、相談から対応、再発防止までを一連の流れとして継続的に改善する姿勢が求められます。
まとめ
苦情ハラスメントは、従業員に大きな心理的負担を与える深刻な問題です。企業はまず、どのような行為が苦情ハラスメントに該当するのかを明確に定義し、従業員へ周知することが必要です。そのうえで、現場ではひとりに任せず複数名で対応し、事実を記録に残し、謝罪や回答の範囲を明確にすることが基本です。危険な状況では速やかに対応を打ち切り、外部機関への相談を行う勇気をもつことも大切です。さらに、社内に相談窓口を設け、教育や研修を行うことが長期的な対策につながります。外部専門家との連携や再発防止策を組み合わせ、企業全体で取り組む姿勢を示すことで、従業員は守られていると感じ、安心して業務に専念できるでしょう。初期対応を整え、相談体制を確立することが、企業の信頼と健全な職場環境を維持するための大切な一歩です。
-
 引用元:https://www.safetynet.co.jp/
心の専門家集団による"自社専用のハラスメント対策"
引用元:https://www.safetynet.co.jp/
心の専門家集団による"自社専用のハラスメント対策"- Point
導入実績:法人企業2,000社+中央省庁、自治体他 / 年間33万人
- Point
会員数:150万人
- Point
専門家在籍:公認心理師、産業カウンセラー、臨床心理士、看護師、栄養士、ファイナンシャルプランナー、警察OB など
- Point