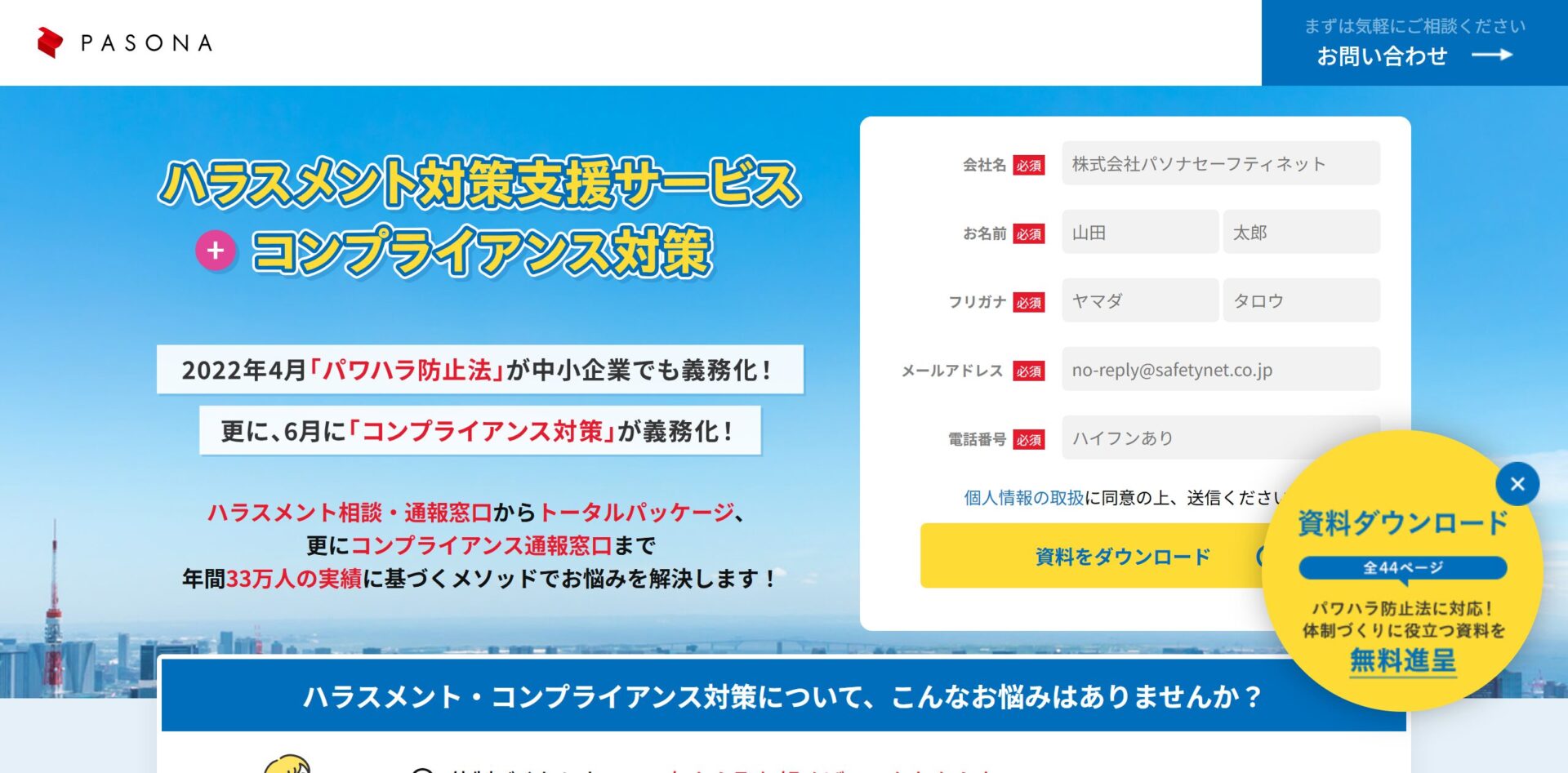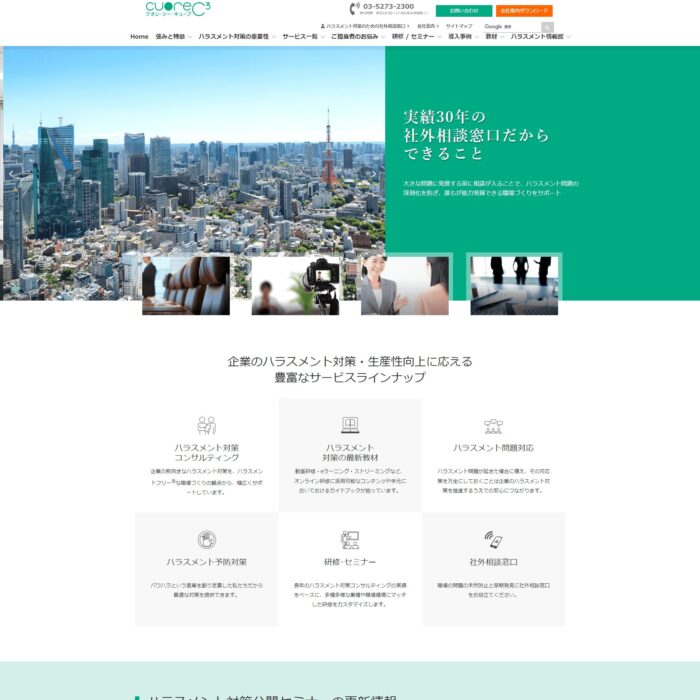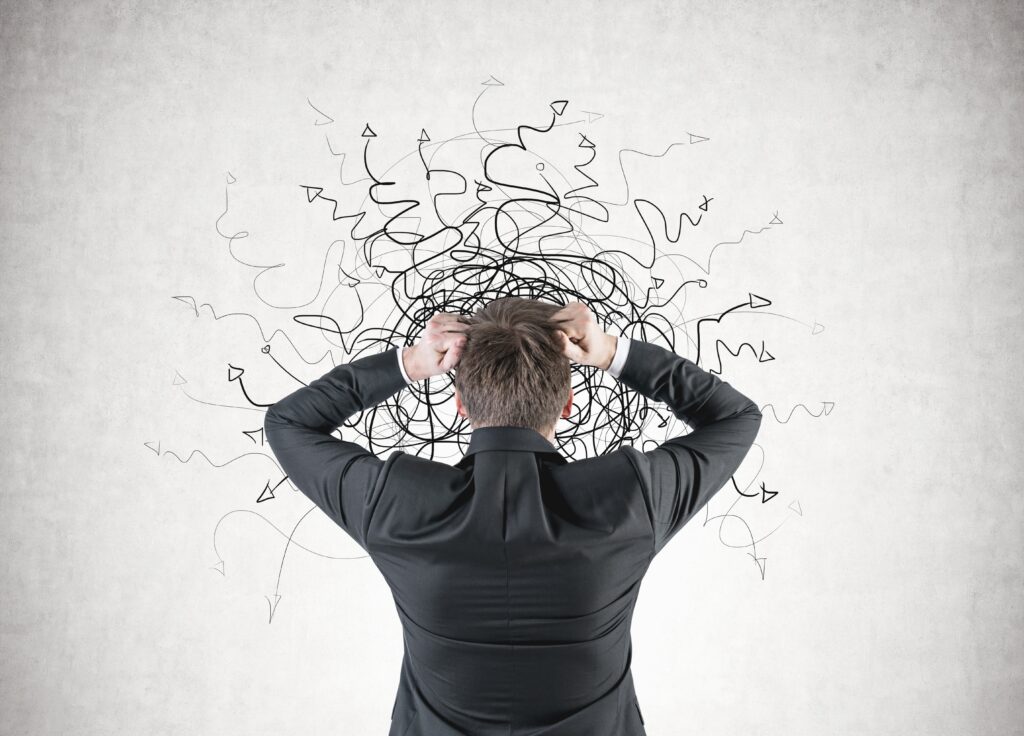就活ハラスメントとは?
近年、企業の採用活動において、応募者に対する不適切な言動や対応が社会問題として注目されるようになっています。たとえば、性的指向・性自認に関する質問、容姿や家庭環境への干渉、交際相手の有無など、採用とは直接関係のないプライベートな事項に踏み込む行為は、面接や面談の場で頻繁に見られる事例として指摘されています。
こうした行為は「就活ハラスメント」と呼ばれています。応募者に精神的な負担や不快感を与えるだけでなく、企業の信頼性や社会的評価にも影響を及ぼす深刻な問題です。
2024年には、厚生労働省が就職活動中の学生などをハラスメントから守るための指針を強化しました。企業に対しては、OB・OG訪問やリクルーター面談のルールを明確化するよう求める方針案を提示し、あわせて「就活ハラスメント対策リーフレット」の配布や、関係法令の周知を進める動きが活発化しています。
さらに2025年6月、参議院本会議では「就活ハラスメント防止」を明記した雇用対策法の改正案が可決され、ハラスメントのない就職環境づくりが国の方針として打ち出されました。法改正により、企業にはハラスメント防止への努力義務が課され、厚生労働省が策定する基本方針に基づいて社内体制の見直しや教育の実施が求められることになります。
今後、採用活動の場においては、学生や求職者にとって安心できる環境を整えると同時に、企業側の倫理観や対応力がこれまで以上に問われる時代へと移行していくと考えられます。
学生の4人に1人がハラスメント被害を受けた経験がある
厚生労働省が公表した「令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、求職活動中の学生の約4人に1人が、何らかのハラスメント被害を受けた経験があると回答しています。この数字からも、就職活動におけるハラスメントは、広く存在していることが浮き彫りとなっています。
被害の発生場所や加害者とされる人物は多岐にわたります。たとえば、インターンシップ先で接した社員や、企業説明会・採用面接の担当者、さらには大学のOB・OG訪問を通じて接触した企業の従業員など、学生が就職活動で接点を持つ多くの立場の人々が加害者として挙げられています。
実際に行われたハラスメント行為の内容としては、「性的な冗談やからかい」が約4割を占めており、セクハラに該当する言動が多くの学生を悩ませている現状が明らかになっています。そのほかにも、食事やデートへの執拗な誘いや性的事実関係に関する質問などが広く報告されています。学生は立場上、対等な関係で意見を言いにくく、泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
今後は、企業側が採用活動における全ての接点でハラスメント防止意識を徹底することが求められます。採用担当者だけでなく、インターンシップ担当者や現場社員も含めた取り組みが、学生との信頼関係構築の第一歩となるでしょう。
どのような行為が「就活ハラスメント」に該当するのか
就活ハラスメントは、無自覚で行われることも少なくありません。ハラスメント被害を防止するためには、どのような行為が「就活ハラスメント」に該当するのかを理解することが重要です。
性的な事実関係に関する質問
面接や面談の場で、性別や恋愛関係、結婚・出産の予定など、性的な事実関係に関する質問をすることは、明確なハラスメントに当たります。採用活動に必要な情報とは認められず、応募者の価値観やプライバシーを侵害する行為です。
また「結婚後も働き続けたいですか」「出産後も働くつもりがあるのか」といった質問を女性学生のみに行う行為は、男女雇用機会均等法に触れる恐れが高いため、注意しましょう。
立場の優位性を悪用した執拗な誘い
就職活動においては、企業が「選ぶ側」であるという構造上、求職者は社員や担当者による誘いを断りづらい状況に陥るケースが少なくありません。
たとえば「内定がほしいなら飲みに行こう」「うちの会社に入りたいなら、もう少し仲良くなろう」といった発言は、立場の優位性を悪用した不適切な誘導です。採用活動中は、節度ある対応を心がけましょう。
圧迫面接
応募者に対して過度なストレスを与えるような面接手法も、就活ハラスメントの一種です。
高圧的な口調での問い詰めや人格を否定するような言動は、学生に精神的ストレスを与えます。採用担当者は、正当な評価と公平な接し方を学んだうえで、面接に臨むようにしましょう。
-
 引用元:https://www.safetynet.co.jp/
心の専門家集団による"自社専用のハラスメント対策"
引用元:https://www.safetynet.co.jp/
心の専門家集団による"自社専用のハラスメント対策"- Point
導入実績:法人企業2,000社+中央省庁、自治体他 / 年間33万人
- Point
会員数:150万人
- Point
専門家在籍:公認心理師、産業カウンセラー、臨床心理士、看護師、栄養士、ファイナンシャルプランナー、警察OB など
- Point